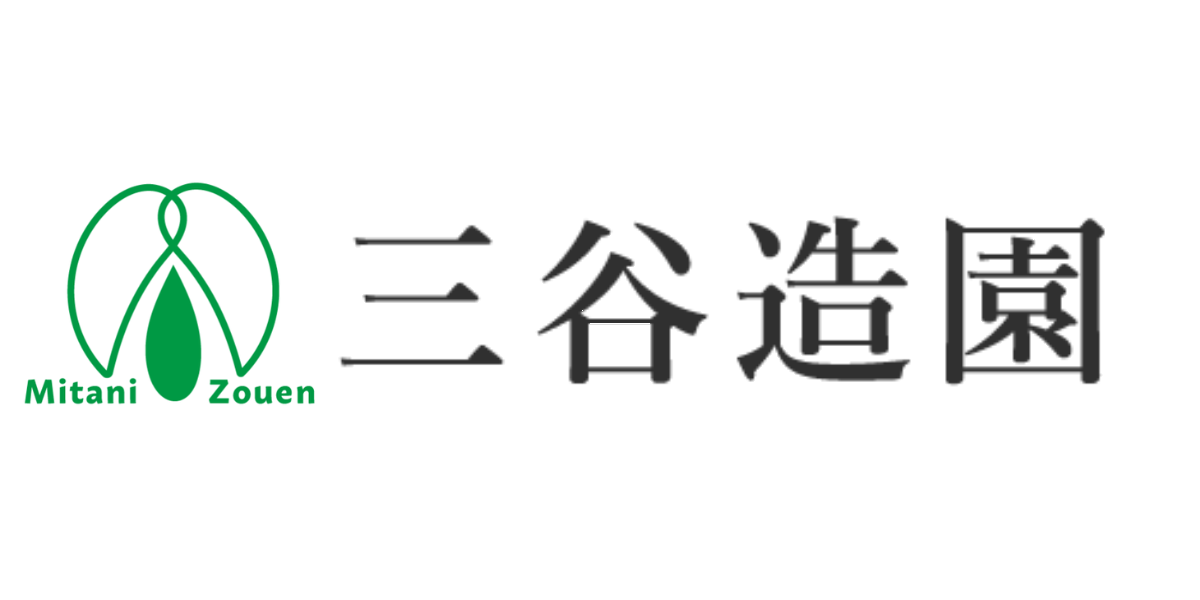植栽管理の具体的な作業内容とは?植栽管理のメリットとその効果
植樹とは単純に樹木を植えることですが、植栽には景観を整えるという意味合いが込められています。
マンション、オフィス、各種施設などの外観を整えたり、道路や公園など公共的な施設の快適性を高めたりするものです。
このような植栽の管理と、他の設備関連の管理とでは一つ大きな違いがあります。
それは、植栽管理が他の設備とは違い、「生きて生長する植物」を対象としている点です。
そのため、植栽管理には植物そのものの知見だけでなく、気候や地域性、立地条件に配慮することが必要になります。
この記事では、植栽管理の概要や具体的な方法について詳しく紹介していますので、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてください。
目次
- ○ 植栽管理で押さえておきたい基本的な知識とは?
- ・植栽管理の目的とは?その重要性と具体的な効果を徹底解説
- ・プロが教える植栽管理の重要性と効果的な方法とは?
- ○ 効率的な植栽管理のメンテナンス方法を紹介
- ・①水やり
- ・②施肥
- ・③剪定
- ・⑤病害虫対策
- ○ 植栽管理の効果とメリットを徹底解説!美しい庭づくりの秘訣とは?
- ○ 植栽管理を業者に依頼するメリットとは?プロが解説するポイント完全ガイド
- ○ まとめ
- ○ 庭のお手入れなら、三谷造園へ
植栽管理で押さえておきたい基本的な知識とは?
植栽管理で押さえておきたい基本をまとめました。
エリアごとの環境条件
植栽地の土壌の状態
植栽されている植物の管理の難易度
例えば、マンションなどの場合、アプローチやエントランス、
中庭などで人通りや陽当り、風通しが違うことがあるので注意が必要です。
肥沃な土壌ほど植物は良好に育ちやすく、自然の樹形のままで美しい木よりも、仕立物は管理に手間がかかります。
上記を踏まえ、植栽管理の目的と重要性について説明します。
植栽管理の目的とは?その重要性と具体的な効果を徹底解説
植栽管理の目的は、木や草花などが良好に生長する条件を整え、美しい景観や植栽がもつ効果を維持することです。
十分に管理された植栽は、建築物の資産価値や利用者の快適性を高めます。的確な管理によって育成・維持された植栽の具体的な効果をまとめました。
・修景効果 |建築物や構造物とともに景観を美しく整える
・資産価値の向上 |美しい景観は大きな付加価値となる
・侵入防止 |生垣や植込地で不審者の侵入を防止する
・環境保護 |地球温暖化やヒートアイランドを軽減する
・住環境の向上 |日差しや風、騒音などを遮断する
・防災効果 |延焼を防止し熱風や旋風を軽減する
・プライバシーの保護|外部からの視線を遮る
植栽があることで、利用者は季節の移ろいを実感したり、花や実がつく植物であれば収穫の喜びを味わったりすることもできます。
プロが教える植栽管理の重要性と効果的な方法とは?
植栽管理は、植栽がもつ様々な効果を維持するように条件を整えるのが目的で行われます。
植栽を放置すると、枝葉は伸び放題となって支障となり、病害虫を発生させて利用者の健康を阻害します。
わが国には四季があり毎年繰り返されるため、植栽管理を年間単位で考えることが多いです。
また、管理が行き届いた樹木は数十年に渡り生育するため、さらに長期的な視野も必要となります。
年間管理では、水やり、施肥、剪定、除草、病害虫対策が植栽管理のための効果的な方法としてスケジュールに組み込まれます。
スポットとして行われるのは、補植や植替え、間引きや伐採などです。
この年間管理は、対象となる植物の生育段階で微調整されるものです。特に、樹木の生育段階には以下のものがあります。
【活着期間】
|環境に順化し根付くまでの期間(植栽~3年)
↓
【育成期間】
|十分に根付き大きく成長する期間(4~10年)
↓
【抑制期間】
|大きくなり過ぎないよう成長を抑制する期間(10~25年)
↓
【更新期間】
|衰弱や枯れを迎える期間(25年~)
管理対象となる樹木や植物の生育段階を見極め、適切な管理を行うことが求められます。
効率的な植栽管理のメンテナンス方法を紹介
効率的な植栽管理のメンテナンス方法には、水やり、施肥、剪定、除草、病害虫対策があります。管理の対象となる植物の特徴、植えられている土壌の状態や生育段階、環境などを考慮して適切なメンテナンスを行うことが必要です。
例えば、施肥の頻度や量は土壌が痩せているか肥沃かで違いますし、花や実をつける植物は肥料分を多めに必要とすることが多いです。虫の発生も、植物の種類や環境で違ってきます。
メンテナンス方法の内容を検討する際のポイントを、
水やり、施肥、剪定、除草、病害虫対策に分けて解説します。
①水やり
植物は光合成をするときに水を必要とします。また、植物は葉の裏にある気孔を通して水蒸気を空中に発散させる蒸散作用によって、水や栄養を体の隅々に循環させます。
このように、水は植物にとって欠かせないものであり、水やりは非常に大切です。植物の成長を助ける効果的な水やりの頻度と量、水切れのサインについて説明します。
植物の成長を助ける効果的な水やりの頻度と量
植物の水やりは、表土が乾いたらたっぷりと与えるのが基本となります。土壌中から水分や栄養を吸収する根だけでなく、光合成の主役である葉の表面にも水やりするのが効果的です。
水やりは地域の気候にもよりますが、年間を通して行うのが一般的です。ただし、季節によって頻度や量を調整する必要があります。
季節ごとの水やりの頻度と量の目安は以下のようになります。
【春と秋】
大幅な気温上昇はない時期のため、表土が乾いた水やりをします。
鉢植えで1~2日に1回、地植えでは3~4日に1回程度が目安です。
【夏】
気温が上昇し、土壌が乾きやすくなるため、水やりの頻度を増やさなければなりません。
朝夕のまだ温度が上がりきらない時間帯に、
鉢植えは1日1~2回、地植えは1日1回程度を目安とします。
日中の水やりは、土壌の温度が急上昇させるので絶対に避けてください。
【冬】
植物の生育は穏やかになり、土壌の乾燥も抑えられる時期のため水やりの頻度を減らします。
表土が乾いてから3~4日後に、鉢植えでは週に1~2回、地植えは2週間に1回程度を目安とします。
ただし、冬でも乾燥することはあるのでチェックは必要です。
水切れのサインとは
水切れのサインとは、水不足によって起きる木や草花の見た目の変化のことです。水切れの状態の植物は、葉がしおれて、葉の色は緑から黄色や茶色に変色してきます。
この水切れのサインを早めにキャッチして植物の状態を読み、水のやり方や頻度を調整することが必要になります。
個人の庭園では住む人が庭を毎日のように眺めているため、植物の水切れのサインに気がつきやすいです。しかし、マンションなどの植栽管理業者は、現場に常駐しているわけではないので住民が先に水切れに気づくことがあります。
こういう場合は、管理組合の方が状況を植栽管理業者に伝え、必要であれば定期巡回前であっても対応を依頼すべきでしょう。
②施肥
植栽管理の施肥とは植物に肥料を与えることです。土壌の活力を増大させ、植物の病害虫に対する抵抗力を高めて、健全な生育と開花や結実を促進するために行われます。
肥料は、植物の三大栄養素である窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)を中心に、カルシウムやマグネシウムなどを含むものが多いです。
ここでは、肥料の種類と選び方、適切な施肥の時期と量について紹介します。
肥料の種類と選び方とは
木や植物に与える肥料の種類は、大きく有機質肥料と無機質肥料の2つに分けられます。
有機質肥料は、動物や植物由来で、成分が溶け出すスピードが緩やかで効果が持続しやすいです。発酵鶏ふん、牛ふん、油粕、骨粉、魚粉、米ぬかなどがあります。
無機質肥料は、鉱物などの原料を科学的に合成して作った肥料で、効果の速効性は高くなります。有機質に比べるとニオイが少なく扱いやすいですが持続性に劣り、長期間繰り返し使用すると土壌に影響を与えるので注意が必要です。
施肥をする時期によっても分類がありますので、以下にその例をまとめました。
【元 肥】
・植栽前に土壌に与える肥料で有機質系のものを混合して与えることが多い
【寒 肥】
・樹木が休眠中の冬期に与える肥料で元肥の一種
【追 肥】
・生育旺盛な時期に与える肥料で速効性肥料を数回に分けて与える
【お礼肥】
・植物の開花後や結実後に与える肥料で追肥の一種
特に、草花や野菜では、肥料が切れないように頻繁に追肥するのが一般的です。
適切な施肥の時期と量を紹介
肥料には、適切な施肥の時期と量があります。木と草花では、施肥のやり方に違いがあるので概要を以下にまとめました。
【木の施肥の時期】
・冬季(12月~2月) /春からの芽吹きに備え栄養を蓄えるため
・花後・結実後 /開花や結実により消費した栄養分の補充のため
【木の施肥の量(目安)】
・高木(樹高4~5m)/300~500g
・中木(樹高2~3m)/100~150g
・低木(1m前後) /20~50g
肥料は根や幹元に与えるのではなく、木の大きさにより、幹から30~50㎝離して木の周囲の土に埋めたり混ぜたりして与えます。
草花の肥料は生育期に与えるのが基本ですが、土壌の状態によっては植え付け前に元肥として土に混ぜ込んで与えることもあります。休眠期は、養分を吸収しないので必要ありません。
草花の肥料は、顆粒や粉状の化成肥料か希釈して使う液体肥料が多いです。施肥の量は、種類によって違いますので、必ず商品に記載されている用法用量を確認しましょう。
植物の見た目から生育の状態を読み、スポット的に与えることもあります。木の樹皮の剥がれや変色、花付きが悪い、葉色に生気がない場合などです。
③剪定
剪定とは、木の生育や美観にとって支障となる枝葉を取り除く作業のことです。
似た用語に刈込がありますが、刈込は主に生垣や寄植えなどの枝葉の先端を切りそろえて整える剪定のことになります。
木は種類によって適切な剪定の時期があり、それを把握して剪定しないと開花や結実がなくなったり、枯れたりすることがあるので注意が必要です。
剪定の目的と方法とは
木を剪定する目的は、主に以下の3つです。
① 美観・機能の維持|木の美しさや効果を保つため
② 病害虫防除 |効率的な日照と風通しを確保する
③ 生育の促進 |移植や災害による木のダメージを軽減する
上記のような目的を達成するための剪定方法の代表的な例を挙げます。
【切詰め剪定】
・主に新生枝を一定の場所にできる芽の直上で切り取る
【切返し(切戻し)剪定】
・適正な分岐点より長い方の枝を付け根から切り取る
【枝抜き(枝透かし)剪定】
・主に込みすぎた部分の枝を透かすようにすること
【枝おろし剪定】
・一般的に鋸を用いて太枝を切り取ること
剪定によって姿を整えることで、木は美しく枝を伸ばし、虫がついたり病気を発生したりしない良好な生育を確保することができます。
剪定時期と注意点まとめ
雑草は繁殖力が旺盛で、植栽が必要とする土壌中の養分や水分を奪い成長を妨げます。雑草が日光を遮り、植栽の光合成を阻害することもあります。
雑草を放置すると、虫や病気を引き起こす感染菌の温床となりやすいです。また、小動物が住み着くこともあります。
雑草の種子は、風や雨、鳥などによって空中から飛来し、人の衣服や靴の裏に密着して運ばれてくるので一度除草してもすぐにまた発生する可能性が高いです。
そのため、植栽管理では、定期的な除草作業が求められます。
効果的な除草方法を紹介
効果的な除草方法には、草取り、草刈り、除草剤散布などがあります。また、防草シートと砂利や人工芝を組み合わせて、長期に渡って雑草の発生を抑制する雑草対策もあります。
草取りとは、雑草を根から抜く除草方法で人力での作業が中心です。草刈りは、刈払い機や自走式草刈り機を使って作業することが多いです。
除草剤散布は薬剤を撒いて除草する方法で、他の植物やペットなどへの影響を考慮したり、作業時の天候を確認したりすることが必要になります。
特に、マンションやアパートでは住民に作業日時を周知することが大切です。
刈草は飛び散りやすいため、作業中の安全管理や作業後の清掃には十分な配慮が必要です。
⑤病害虫対策
病害虫対策の基本は、虫や病気が発生しにくい環境を整えることです。植栽エリアの日当たりや風通しを良くして、落ち葉や花がらなど病害虫発生の原因になるようなものを速やかに取り除くことが肝心です。
これらを踏まえて、植物の病気や害虫対策について紹介します。
植物の病気と害虫対策
木や草花につく虫や病原菌の対策には、駆除と防除があります。駆除は、すでに発生している病害虫を取り除くことで、防除は病害虫の発生や侵入を未然に防ぐことです。
駆除方法の中心は薬剤散布ですが、病害虫の天敵となるような昆虫や植物を利用することもあります。最近では環境への配慮から、各種酢液や重層水を使用することも多いです。
防除では、対象となる病害虫に応じた適切な時期に薬剤(主に殺菌剤)などを散布します。
害虫の防除を行う時期は、地域の気候や虫の種類によって違います。一般的には、虫の活動がピークを迎える前の4~5月頃に行うことが多いです。
病気の対策は、植物が生育期を迎える前の5月頃から対策を講じます。
植栽管理の効果とメリットを徹底解説!美しい庭づくりの秘訣とは?
植栽管理は、植物の生育環境を整えることで、植栽の目的や機能を達成させて維持します。
それにより、建築物や構造物の資産価値を高めると同時に、住民生活の快適性を向上させます。
また、目的や機能が維持された植栽は、直射日光や強風、騒音を緩和し、外部からの視線を遮断してプライバシーを保護することが可能です。
住民に安らぎを与える美しい庭は、植栽ボリュームの追及や意表をつくようなデザイン、目新しい木の植栽から生まれるものではありません。
地域の気候風土に適した木や草花、芝生などを選定し、その植物に合った剪定や施肥、病害虫対策などの植栽管理から生まれます。何故なら、そのような植栽は季節の移ろいとともに生き生きと生長するからです。
自然な状態で生長する植栽を観ることで、住民は自然とともにあることを感じ、癒しを得ることができます。
植栽管理を業者に依頼するメリットとは?プロが解説するポイント完全ガイド
植栽管理を専門業者に依頼することで、作業の年間スケジュールや予算を「見える化」できます。また、専門業者の豊富な知見と経験に裏打ちされた高い技術は、植栽の健全な生育に反映されます。
一般の方の中にも、植物の手入れが好きな方は多いです。しかし、単純に好きな方とプロでは、同じ作業をしても違いがあります。
プロが木を剪定すると、その木がもつ本来の美しい樹形を保つのに必要な枝は残し、不要な枝は切り取ります。枝についている芽の違いがわからない一般の方には難しい作業です。
また、プロは、どの枝を残せば数年後にどのような樹形になるかを想像しながら剪定することができます。一般の方は、自分が好きなように、手入れをしやすいように枝葉を切るだけでしょう。
剪定を例に違いを紹介しましたが、その他の作業においても、豊富な知見や実績、高い技術をもつプロに依頼するメリットがあります。
まとめ
ここまで、植栽管理について、以下の内容で紹介してきました。
植栽管理の基本について重要性と効果的な方法から説明
効率的な植栽管理を水やり、施肥、剪定、除草、病害虫対策のポイントで紹介
植栽管理の効果とメリットから美しい庭づくりについて説明
植栽管理を業者に依頼するメリットのポイントを紹介
植栽管理とは、植栽がもつ目的や効果を達成し、維持することです。そのためには、剪定や水やりから、施肥、虫の防除に至るまで、専門的な知識が求められます。
特に、マンションなどの植栽は、住民の方々の共同スペースです。責任をもって業務を実践できる業者に依頼することが、安全で安心な植栽管理へと繋がります。
庭のお手入れなら、三谷造園へ
店舗や病院、マンションなど多くの人が出入りする場所では植栽管理が重要です。駐車場やお店の周りの植木が荒れ放題では印象も悪くなりますね。
三谷造園では店舗やマンションからのご依頼も承っております。過去の施工例をご覧いただき、是非ご検討ください。
シェアする